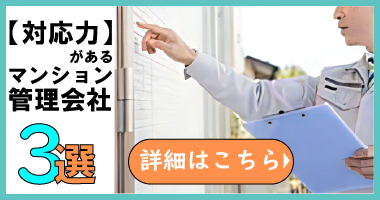
分譲マンションは、理事会役員がマンション運営におけるルール作りなどを行っています。しかしながら理事会役員のなり手不足に陥っているマンションも少なくありません。だからこそ外部の専門家に理事を依頼する「第三者管理方式」に注目が集まっているのです。
このページでは第三者管理方式とは何か、メリット・デメリットなどを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
第三者管理方式とは外部の専門に理事長や役員に就いてもらい、管理組合の運営を委託することです。
一般的にマンション管理は所有者による理事会運営方式が行われ、専有部分を所有している方は管理組合を作り、実際の業務に関しては管理会社に委託するケースがほとんどでしょう。
一方、第三者管理方式の場合、修繕積立金の管理・総会の開催・修繕計画の作成・住民報告など、理事会が行うべき業務を外部の専門家に任せます。専門的知識を有したプロによる管理組合をサポートが受けられます。
第三者管理方式の外部専門家はマンション管理士・弁護士・司法書士・建築士などが相応しいでしょう。
近年、さまざまな問題から第三者管理方式を採用しているマンションは増えていると言われています。ここでは第三者管理方式が増える理由について見ていきましょう。
第三者管理方式が増えた理由として、所有者の高齢化が進んでいるからです。とくに築年数が経ったマンションの場合、区分所有者の高齢化が進んでいるケースも多く、マンション理事や管理運営に関心が低くなっています。また高齢者だと理事の業務自体の負担が多くなってしまい、身体的にも業務が難しくなるでしょう。だからこそ理事会業務を第三者に委託するケースが増えてしまうのです。
マンション自体の老朽化も問題の一つです。国土交通省によると築40年以上のマンションは2021年時点で115万戸以上になると報告されており、年々築40年以上のマンションは増加すると見込まれています。それほどの年数が経っていればマンション全体に不具合も起こりやすく、大規模修繕工事が必要となるでしょう。 しかし若い世代が入居しなければ居住者の高齢化が進んでいるマンションとなり、大規模修繕工事をきちんと行えるかという問題も発生します。マンション維持の観点からも適切な人材がマンション管理に関わっていく必要があるのです。
参照元:国土交通省「マンションを取り巻く現状について」【PDF】
標準管理規定とは、マンションの管理規約のひな型のようなもので、国土交通省が作成しているものです。この標準管理規約ではマンションに住む人による自治がメインとなり、居住者で構成する理事会がメインでマンション管理を行うことを前提に作成されていました。しかし住民による自治自体が難しくなっている現状もあり、平成23年には理事の要件のなかから「マンションに現に居住する」という文言が撤廃されています。さらに平成28年の改定では「外部専門家を役員として選任できることとする」という条文が加えられ、これによって外部の専門家がマンションの理事に就任可能になったのです。
一般的にマンションの理事・役員に就いてしまうと、休日などの空き時間を利用してマンション業務を行わなければなりません。仕事や家事などで日々多忙にしている方にとっては、大きな負担を感じやすく、現実的にマンション業務が難しいとなってしまいます。その結果、理事会に積極的に参加する人は少なくなり、担い手不足の状態に陥ってしまうでしょう。これまでボランティアのように行っていた業務を、業務の対価を支払い第三者管理方式にて外部の専門家を介入させる方法にシフトするケースも増えています。
基本的にマンションの資産価値は新築時が最高であり、徐々に資産価値は低下していく傾向にあります。少しでも資産価値を維持するためには、適切な管理を徹底することが大切です。その意味でも専門的な知識を持った外部に任せることも重要になってくるでしょう。地域のマンション事情をはじめ、社会情勢の影響などを総合的な視点でマンション運営を考えられる専門家が欠かせない存在になるのです。
第三者管理方式と言っても、方法は1つだけではありません。理事会の構成メンバーの中に外部の専門家を招く方法・理事会を残し外部の専門家が理事長に就く方法・理事会自体を廃止する方法の3つがあります。ここでは、それぞれの方式について見ていきましょう。
マンション管理士などの専門家がマンションの管理責任者という立場になる方式です。外部の専門家が理事会の一人となり、区分所有者とともに管理組合の運営に携わります。理事会では管理会社の選定・大規模修繕工事などの比較検討などを行うため、専門家かつ客観的な立場で運営のサポートを実施。そのため選任された理事の負担軽減にもつながります。ただし外部専門家が工事会社などと結託する恐れもあるので注意が必要です。
外部の専門家を理事長として選任し、理事会側が外部管理者を監視する方式です。外部の専門家を区分所得者だけで構成される理事会を監視する立場や、理事会とは分断した管理者として配置を行います。区分所有者から人を選任し監視するだけでなく、監査法人など外部の監査を義務付ける場合も。
区分所有法上の管理者とマンション標榜管理規約の理事長の両者の役割は、ほとんど変わりません。しかし標榜管理規約の理事長の方が細かなルールなどが多いため設定されている方式です。
この方式を採用することによって、管理費などの滞納の回収・被災対応・反社会勢力への対応など様々な問題に柔軟に対応できる体制が整うでしょう。ただ外部専門家が工事施工会社などと結びつき、管理組合の不利益に及ぶ行為を行うリスクがある点は理事腸外部専門家と同様です。
次に理事会自体を廃止して、マンション管理士などの専門家がマンションの管理者として就く方式です。この方法は理事会がなくなるため、区分所有者から選ばれた監事が外部専門家を監視する、または監査法人による外部監査を行わなければなりません。外部の専門家にほぼ委託する方法なので、組合の負担は大幅に軽減できるでしょう。ただ外部の専門家が不正を行う恐れがあるため、しっかりと管理組合がチェックすることが大切です。
第三者管理方式は必ずしもメリットばかりではありません。メリットやデメリットを把握しておかなければ後悔する恐れもあるでしょう。ここでは第三者管理方式のメリット・デメリットを紹介します。
マンションの管理組合は身体的だけでなく、精神的な負担も大きな業務を行わなければなりません。第三者管理方式を採用することで、管理組合の負担軽減も図ることが可能です。当番制で理事を回ってくるケースも多く、参加が難しい区分所有者もいるので理事の選出に労力を要する恐れもありますが、第三者管理方式なら理事の選出の労力も削減できるでしょう。
内輪だけでマンション管理を行っていると、とくに必要のない会議であっても開催するケースが多々あります。こうした課題も外部に委託することで、必要なときにだけ理事会を開催となり解消を図ることができます。また理事会自体を廃止に出来るため、理事の担い手不足問題の解消も図れます。
理事会ではマンション管理の全てを取り仕切るため、日常的な工事だけでなく大規模修繕工事などの計画・発注も実施しなければなりません。外部の専門家が介入することによって、専門的な知見を知ることもでき、管理業務の効率化をアップできるでしょう。マンション管理のプロが関わるため、区分所有者だけの理事会よりも運営の質が高まりやすくなります。
区分所有者がボランティアのような形で行っていた業務を外部に委託するため、外部専門家に対する支払いが発生します。その分の管理費が割高となる点は留意しておきましょう。区分所有者から管理費増額の理解を得たうえで第三者管理方式を採用しなければなりません。
外部の専門家が必ずしもマンション側の利益を追求するとは限らない、という点も注意しておきましょう。マンションの組合員が望まない運営を行う場合もあり、業者と癒着をして不利益を及ぼすケースもあります。区分所有者が不利益にならないようにチェック体制を厳しく設けておくことが大切になってきます。
第三者に任せることによって、マンション自体で管理組合に関するノウハウを習得することが難しくなります。マンション管理に関する運営ノウハウは、長年にも渡り受け継ぐケースがほとんどなので、一度第三者管理方式に変更してしまうと従来の管理方式に戻すのは難しくなります。
管理会社への不満やマンション内の悩みがあっても、 どのように解決すればよいかわからないですよね。 このサイトでは、困りごとを解決できるマンション管理会社3選を紹介していますので こちらもぜひご覧ください。



選定基準:
一般社団法人 マンション管理業協会に属し、埼玉県に事業所・支店があるマンション管理会社の中から、担当者の担当棟数を10件以下に制限している3社を選出。
・ホームライフ管理…事務管理から建物の管理(大規模修繕工事の実行まで)をワンストップで対応している。
・三興管理……独立系マンション管理会社で、HP上でリーズナブルな価格について言及している。
・マリモコミュニティ……マンション内のコミュニティのサポートを行っている。
として選出しました。